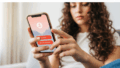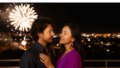急な転勤で知らない土地に来て、休日に話し相手もいない…。30代前半になると、新しい環境で友人を作るのって、なんだか難しく感じますよね。
せっかく夢中になれる趣味があっても、その感動を分か-ち合える人がいないと、だんだん楽しさも半減してしまうかもしれません。
この記事は、まさにそんな悩みを抱えていた男性の、リアルなpcmax体験談なんです。彼が、凍えるほど孤独だった日常を、たった一つの出会いでどのように変えていったのか。そのきっかけは、カメラという共通の趣味でした。
もちろん、アプリでの出会いって、少し勇気がいりますし、本当に誠実な人と出会えるのかなって不安に思う気持ちも、すごくよく分かります。
でも、彼の物語を読んでもらえれば、ただの暇つぶしではない、心温まる繋がりの可能性をきっと感じてもらえるはずですよ。
\『大人の関係作りNo.1!』/
プロローグ:白銀の世界と、凍てつく心
「辞令だ。来月から札幌支社に転勤してもらう」
課長から無機質なトーンで告げられたその言葉を、僕は最初、うまく理解できなかった。ケンジ、33歳。東京の食品メーカーで商品企画を担当し、仕事にもプライベートにも、それなりの手応えを感じていた矢先のことだった。
札幌。その響きには、どこかロマンチックな憧れがあった。美味しい海産物、広大な大地、美しい雪景色。東京のコンクリートジャングルに疲れていた僕にとって、それはむしろ「ご褒美」のようにすら思えた。「北海道で新しい商品を企画するんだ!」そんな野心を胸に、僕は期待に胸を膨らませていた。
しかし、現実は小説のように甘くはなかった。
僕が札幌に降り立ったのは、11月の末。街はすでに白銀の世界に包まれていた。最初は感動していた雪も、日々の生活にのしかかる重荷に変わるのに、そう時間はかからなかった。毎朝の雪かき、ツルツルと滑る恐怖の雪道運転、そして何より、骨身に染みる寒さ。
だが、物理的な寒さ以上に僕の心を凍てつかせたのは、圧倒的な「孤独」だった。
東京には、仕事終わりにくだらない話で笑い合える同期がいた。週末にはフットサルチームの仲間がいた。行きつけのバーには、気さくなマスターがいた。ここ札幌には、誰もいない。職場の人間は皆、親切だが、やはりどこか壁がある。仕事が終われば「お疲れ様」の一言で、蜘蛛の子を散らすように帰っていく。
週末が来ることが、苦痛だった。広々とした1LDKの部屋で、一人。窓の外では雪がしんしんと降り積もり、世界から音が消えていく。その静寂が、僕の孤独を際立たせた。やることがない。話し相手もいない。時間だけが、無情に過ぎていく。
僕には、カメラという趣味があった。東京にいる頃は、週末になると愛機のSONY α7 IIIを片手に、街のスナップや風景を撮り歩くのが何よりの楽しみだった。札幌に来てからも、最初は意気込んでいた。「あの美しい風景を、自分の手で切り取ってやる」と。
だが、一人で重い機材を担いで、凍える寒さの中へ出ていく気力は、日に日に削がれていった。撮った写真を見せる相手もいない。感動を分か-ち合う相手もいない。ファインダーを覗いても、そこに写るのはただの冷たい景色。僕の心と同じ、モノクロームの世界だった。気づけば、防湿庫にしまったカメラの蓋を開けることすらなくなっていた。
「このままじゃ、ダメになる」
無気力な日々が1ヶ月ほど続いた頃、強烈な焦燥感に襲われた。この凍てついた心を溶かしてくれる何か、誰かを見つけなければ。このままでは、仕事のパフォーマンスにも影響が出る。僕は、すがるような思いでスマホを手に取った。
いくつかのアプリを比較検討した結果、僕が選んだのは「PCMAX」だった。決め手は、地方都市のユーザーも多く、趣味のコミュニティ機能が充実しているという評判だった。下心がないわけではなかったが、それ以上に、ただ純粋に「同じ趣味を持つ誰かと繋がりたい」という気持ちが強かった。この無味乾燥な日常に、彩りを与えてくれる出会いを求めて。
第一章:ファインダー越しの「いいね!」

PCMAXに登録し、プロフィール作成に取り掛かる。写真が命だということは知っていた。僕は、これまでの自信作の中から、富士山の麓で撮った朝焼けの風景写真を選んだ。顔写真は、少し恥ずかしかったが、カメラを構えている横顔の写真を設定した。これなら、カメラ好きだということが一目で伝わるだろう。
そして、自己紹介文。ここで僕のすべてが決まる。何度も推敲を重ね、こう書き込んだ。
「はじめまして、ケンジです。仕事で東京から札幌に転勤してきました。慣れない土地で、少し寂しい毎日を送っています(笑)。趣味はカメラ(SONY α7 III)です。休日に、札幌近郊の美しい風景を一緒に撮りに行ってくれる方を探しています。おすすめの撮影スポットなど、情報交換だけでも嬉しいです!よろしくお願いします」
ポイントは、①転勤者であること、②孤独であることを正直に伝え、同情を誘う(?)こと、③具体的な趣味と目的を明記し、相手がコンタクトを取りやすいようにすること、だ。我ながら、完璧なプロフィールができたと思った。
しかし、最初の数日は空振りだった。足跡はつくものの、メッセージは来ない。来るのは「今から会えませんか?」という、明らかに業者くさいメッセージばかり。自分から数人に「いいね!」を送ってみても、梨のつぶて。やはり、33歳の男に興味を持つ女性などいないのか。防湿庫のカメラと同じように、僕の心もまた固く閉ざされようとしていた。
諦めかけていた、ある平日の夜。仕事を終えて冷え切った部屋に帰り、いつものようにPCMAXを開くと、一件の「いいね!」通知が光っていた。どうせまた業者だろうと、期待せずにプロフィールを開く。
そこにいたのは、僕と同じようにカメラを構えた女性だった。
『ユキ、33歳』
プロフィール写真の彼女は、満開のラベンダー畑の中で、Canonの白いカメラをこちらに向けていた。その表情は真剣そのものだが、どこか楽しそうだ。他の写真には、彼女が撮ったであろう、息をのむほど美しい美瑛の丘や、小樽運河の夜景が並んでいた。どれも構図が素晴らしく、光の捉え方が絶妙だった。
そして、年齢は僕と同じ33歳。地元、札幌在住。
心臓が、ドクンと大きく鳴った。この人だ。この人しかいない。僕は、震える指でメッセージ画面を開いた。どんな言葉を送れば、僕の気持ちが伝わるだろう。考えに考えた末、シンプルに、そして誠実に送ることにした。
「はじめまして、ケンジです。プロフィール拝見しました。ユキさんもカメラがお好きなんですね!どの写真も本当に素敵で、思わず『いいね!』しちゃいました。特に美瑛の丘の写真、感動しました」
送信ボタンを押してから、5分が永遠のように感じられた。既読の文字がついた瞬間、息を止める。返信は、来るか…?
ピコン。スマホが短く鳴った。
「はじめまして、ユキです!ありがとうございます!ケンジさんの富士山の写真も、すごく綺麗ですね。あのグラデーション、どうやって出すんですか?私はCanonユーザーなんですけど、SONYも気になってて…。よかったら、色々教えてください!」
僕は、思わず「よしっ!」と声に出してガッツポーズをした。凍てついた大地に、小さな春の芽吹きを見つけたような、そんな温かい気持ちが胸に広がった。
第二章:絞り値とシャッタースピード、そしてLINE ID

\『大人の関係作りNo.1!』/
『PCMAXを無料で試してみる(R18)』
僕とユキさんの会話は、まるで堰を切ったように溢れ出した。
PCMAXのメッセージ機能は、僕たちにとって最高のコミュニケーションツールとなった。お互いが使っているカメラの機種、好きなレンズの焦点距離、偏愛する単焦点レンズの話、Lightroomのプリセット自慢…。それは、同僚や東京の友人たちには決して理解されない、マニアックで、濃密で、最高に楽しい時間だった。
ケンジ:「やっぱり単焦点のキレは違いますよね。僕はSIGMAの35mm F1.4が手放せません」
ユキ:「わかります!私はEF50mm F1.8 STM、通称『撒き餌レンズ』ですけど、あの軽さと写りが大好きで。ケンジさんは、RAWで撮って現像する派ですか?」
ケンジ:「もちろんです!Lightroomで追い込む時間が至福です(笑)。ユキさんの写真、すごく透明感がありますけど、何か特別なことしてます?」
ユキ:「えー、嬉しい!ちょっとだけかすみの除去をマイナスに振って、ハイライトを調整するくらいですよ。今度、私のプリセット、見てみます?」
こんな会話が、仕事の合間や寝る前の時間、途切れることなく続いた。僕は、スマホの通知が鳴るのが待ち遠しくて仕方がなかった。ユキさんも同じ気持ちだったようで、返信はいつも驚くほど速かった。
お互いが撮りためた写真を見せ合うのが、日課になった。ユキさんが送ってくれる札幌の日常の風景は、僕が今まで見てきたモノクロームの世界とは全く違った。彼女のファインダーを通した世界は、キラキラと輝き、生命力に満ち溢れていた。
数日が経った頃、僕は一つの課題に直面していた。PCMAXのメッセージ機能では、高画質の写真を送るのに限界があったのだ。これを口実に、次のステップに進む時が来た。
ケンジ:「ユキさん、いつも綺麗な写真ありがとうございます。ただ、サイト経由だと画質が落ちちゃうのが、ちょっと残念で…」
ユキ:「あ、それ私も思ってました!せっかくの素敵な写真がもったいないですよね」
ケンジ:「ですよね!もし、本当に、もしご迷惑でなければなんですが…。LINEなら、もっと気軽に高画質の写真を送り合えるかな、なんて…。ダメなら全然、スルーしてください!」
少しだけ、図々しかっただろうか。送信ボタンを押した指先が、汗で湿る。沈黙の数十秒。
ピコン。
ユキ:「ぜひ!私も色々情報交換したいです!」
続けて、ウサギがぺこりとお辞儀をするスタンプと共に、彼女のLINE IDが送られてきた。僕は、カメラの絞りを開放F値にした時のように、心のピントが彼女一人に合っていくのを感じていた。
第三章:レンズ越しの笑顔と、温かいカフェラテ
LINEでの繋がりは、僕たちの距離をさらに縮めた。
スタンプ一つで感情が伝わる手軽さ。写真の簡単な共有。僕たちは、まるで何年も前からの友人のように、毎日他愛ないやり取りを重ねた。
「今日の夕焼け、綺麗ですよ!」と僕が会社の窓から撮った写真を送れば、「ほんとだ!こっちはもう雪が降ってきました」とユキさんが写真を返してくる。そんな、趣味で繋がった穏やかなコミュニケーションが、僕の荒んだ心を癒してくれた。
ある夜、思い切って電話をしてみた。コール音が2回鳴った後、「もしもし」と聞こえた声は、僕が想像していた通り、明るくて優しい響きだった。30分ほど話しただろうか。文字だけでは伝わらない彼女の人柄に触れ、僕はますます彼女に会いたいという気持ちを強くした。
そして、LINEを交換してから一週間後の週末。僕は、ついに彼女をデートに誘った。
「ユキさん、今週末、もし予定がなかったら…。一緒に写真を撮りに行きませんか?天気も良さそうなので、美瑛の丘あたりまでドライブなんてどうでしょう?」
「行きたいです!」と、即答だった。
約束の土曜日。僕は、この日のために洗車した愛車で、待ち合わせ場所の札幌駅に向かった。どんな服を着ていこうか、どんな話をしようか。まるで初心者のように、心臓がバクバクしていた。
駅の北口で車を停め、ハザードを点滅させて待っていると、ガラス張りの向こうから、ベージュのダウンコートに身を包んだ一人の女性が小走りでやってくるのが見えた。ユキさんだ。
「お待たせしてごめんなさい!」
「いえ、全然!はじめまして、ケンジです」
「ユキです。よろしくお願いします!」
マスク越しでも分かる、屈託のない笑顔。プロフィール写真で見た、あのラベンダー畑での笑顔と同じだった。
高速道路を走り、美瑛へ向かう。車内には、僕が選んだ洋楽のプレイリストが静かに流れていた。最初は緊張していた僕たちも、好きな音楽の話や、最近出た新しいカメラの噂話をするうちに、すっかり打ち解けていた。
美瑛の「セブンスターの木」の駐車場に車を停めた時、僕は思わず息をのんだ。地平線の果てまで続く、真っ白な雪原。その上に、数本の木々が影を落とし、まるで水墨画のような世界が広がっていた。
「すごい…」
「綺麗でしょ?冬の美瑛、最高なんです」
僕たちは、夢中になってシャッターを切った。寒さも忘れ、アングルを変え、レンズを交換し、ただひたすらに目の前の絶景と向き合った。時折、同じ被写体を狙う僕たちの視線が交差し、どちらからともなく笑みがこぼれる。
「ケンジさん、ちょっとそこに立ってもらえませんか?雪と青空のコントラスト、絶対に綺麗に撮れます!」
「え、僕がモデルですか?じゃあ、次はユキさんを撮らせてくださいよ」
僕はファインダーを覗き、ユキさんにピントを合わせた。広大な雪景色の中、少し照れくさそうに、でも嬉しそうに微笑む彼女。カシャッ、というシャッター音と共に、僕は確信した。今日、僕が撮りたかったのは、この笑顔だったんだ、と。
陽が傾き始め、体が芯から冷え切った頃、僕たちは近くのカフェに避難した。木の温もりを感じる、お洒落な空間。温かいカフェラテを一口飲むと、凍えた指先に血が通っていくのが分かった。
「見てください、さっき撮ったケンジさん、めっちゃ格好良く撮れましたよ」
「本当だ。ユキさん、ポートレートも上手いんですね。こっちの、ユキさんの写真も見てください。我ながら傑作です」
カウンター席に並んで座り、お互いのカメラの液晶モニターを見せ合う。自分の写真を褒められるのはもちろん嬉しいが、彼女の笑顔を切り取った写真を見て、「宝物にします」と喜んでくれる彼女の姿を見ている方が、何倍も幸せだった。
カフェラテを飲みながら、僕たちはカメラ以外の話もした。僕は、転勤してきたばかりの不安や孤独を、正直に打ち明けた。するとユキさんは、真剣な眼差しで僕の話を聞き、優しくこう言ってくれた。
「そっか…。大変でしたね。札幌の冬は、地元民でも心が滅入ることがありますから。でも、大丈夫。春になったら、ライラックが咲いて、大通公園がすごく綺麗になりますよ。夏はYOSAKOIソーラン祭りがあって、秋は紅葉が素晴らしい。私が、全部案内しますから」
その言葉は、どんなストーブよりも、僕の心を温めてくれた。
最終章:ファインダーから、僕の隣へ

最初の撮影デートから、僕たちの関係は急速に深まっていった。
週末になるたびに、僕たちはカメラを片手に出かけた。凍てつく支笏湖の氷濤まつり、ノスタルジックな小樽運河の夜景、函館まで足を延ばして、宝石箱のような夜景も撮りに行った。同じ景色を見て、同じように感動し、同じ瞬間にシャッターを切る。その繰り返しの中で、ユキさんは僕にとって、単なる「カメラ仲間」ではなく、かけがえのない存在になっていた。
撮影のない日も、僕たちは会った。美味しいと評判のスープカレー屋に行ったり、話題の映画を観に行ったり。趣味以外の共通点もたくさん見つかった。笑うツボが同じこと、好きな食べ物が似ていること、そして、二人とも少し人見知りなところ。知れば知るほど、彼女に惹かれていった。
ある土曜の夜。僕たちは、札幌の夜景を一望できる藻岩山に来ていた。ロープウェイで山頂にたどり着くと、眼下には無数の光が広がり、まるで宇宙船から地上を見下ろしているような気分だった。
「すごいね…」
「うん、すごい…」
僕たちは三脚を立て、夢中でシャッターを切った。納得のいく一枚が撮れた後、二人で展望台のフェンスに寄りかかり、しばらく黙って街の灯りを眺めていた。吐く息が白い。隣に立つユキさんの肩が、僕の肩にそっと触れている。
今しかない。
そう思った。ここで言わなければ、きっと後悔する。僕は、ゆっくりと深呼吸をして、隣にいる彼女に向き直った。
「ユキさん」
「ん?」
「俺、今日まで、ずっとユキさんのことをファインダー越しに見てきた。でも、もうそれじゃ足りないんだ」
僕の真剣な声に、ユキさんが息をのむのが分かった。
「俺、ユキさんのことが好きです。もう、カメラ仲間じゃなくて、ユキさんの隣に、恋人としていたい。僕と、付き合ってください」
精一杯の告白だった。沈黙が怖い。断られたらどうしよう。凍える寒さとは違う、冷たい汗が背中を流れる。
ユキさんは、しばらく黙って夜景を見つめていたが、やがて、僕の方を向き直り、はにかむように微笑んだ。
「…私も、ケンジさんといると、すごく楽しい。カメラを構えてる時の真剣な横顔も、くだらないことで笑う顔も、全部好き。これからも一緒に、もっと色んな景色を、隣で見ていきたいな」
僕は、彼女の言葉の意味を理解するのに、数秒かかった。そして、喜びが全身を駆け巡った。僕は、おそるおそる彼女の手に、自分の手を伸ばした。冷たい空気の中で触れた彼女の手は、驚くほど温かかった。僕が初めて買った単焦点レンズよりも、ずっと大切で、愛おしい感触だった。
エピローグ:二人で描く未来の設計図
あの日、藻岩山で繋いだ手を、僕たちはまだ離していない。
あれから半年。札幌の長い冬は終わり、街はライラックの香りに包まれている。僕の休日は、もう孤独ではない。隣にはいつも、カメラを構えて楽しそうに笑うユキさんがいる。
僕の転勤には、任期がある。いつかは東京に戻らなければならない日が来るかもしれない。その不安が、ないと言えば嘘になる。でも、僕たちはその話もした。そして、二人で出した結論は、「その時が来たら、また二人で考えよう」ということだった。今は、この札幌で過ごす一日一日を、大切にしよう。そう決めたんだ。
先日、僕たちは新しいカメラを買いに、家電量販店に行った。そして、二人でお金を出し合って、最新のドローンを買った。
「今度は、空から撮ってみようよ。二人でしか見られない景色をさ」
そう言って笑う僕に、ユキさんは「最高だね!」と満面の笑みで答えてくれた。
この体験談を読んでいる、かつての僕のように、慣れない土地で孤独を感じている人がいるかもしれない。そんなあなたに伝えたい。あなたの「好き」は、最高の共通言語だ。そのファインダーで、何を見てみたい?その情熱を、プロフィールに書き込んでみてほしい。
きっとどこかに、あなたと同じ景色を見たいと願っている人がいるはずだから。PCMAXは、そのための、ほんの小さなきっかけに過ぎない。一歩を踏み出す勇気さえあれば、モノクロームだったあなたの世界は、鮮やかなフルカラーに色づき始めるだろう。僕が、そうだったように。
\『大人の関係作りNo.1!』/
「新しい出会いがほしい…」
「気軽に話せる相手を見つけたい!」
そんなとき、PCMAXがあれば解決します。
実は私も最近、PCMAXで気の合う相手と出会い、毎日のチャットを楽しんでいます。 共通の趣味を持つ人との会話は、本当に楽しい!
- ✅ 豊富なユーザー数で理想の相手が見つかる
- ✅ 24時間体制のサポートで安心
- ✅ 趣味や年齢で検索できるから効率的
- ✅ 登録無料!まずは気軽に試せる!
まとめ
ポイント
-
主人公は33歳、札幌へ転勤したての男性である
知り合いゼロの土地での深刻な孤独感がアプリを始めるきっかけだ
趣味のコミュニティ機能が充実しているPCMAXを選んだ
趣味が伝わる風景写真や機材を持った横顔をプロフィールに設定した
自己紹介で転勤者であることや寂しさを正直に伝えた
「一緒に写真を撮りに行く」という明確で健全な目的を提示した
最初は業者と思われる相手からの連絡しか来なかった
同じカメラの趣味を持つ同い歳の女性とマッチングに成功する
最初のメッセージでは相手の写真を具体的に褒め、共通点をアピールした
マニアックなカメラの話題で、メッセージが驚くほど盛り上がった
写真の画質を口実にして、自然な流れでLINE交換を提案した
初デートは趣味を前面に出した「撮影ドライブ」であった
同じものを見て感動を共有する体験が、二人の距離を大きく縮めた
自分の弱みを正直に話すことで、相手との信頼関係が深まった
撮影デートを重ねた後、ロマンチックな夜景スポットで告白した
告白は成功し、モノクロだった日常が彩り豊かなものに変わった
趣味という共通言語が、出会いにおいて最高の武器となり得る